Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 sp. nov., a novel hydrogen-producing bacterium isolated from a deep diatomaceous shale formation
sp. nov., a novel hydrogen-producing bacterium isolated from a deep diatomaceous shale formation上野 晃生*; 佐藤 聖*; 玉村 修司*; 村上 拓馬*; 猪股 英紀*; 玉澤 聡*; 天野 由記; 宮川 和也; 長沼 毅*; 五十嵐 敏文*
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 75(6), p.006802_1 - 006802_11, 2025/06
幌延深地層研究センターの地下施設内に掘削されたボーリング孔を用い、深度350mの新第三紀堆積層中の地下水から、グラム陰性、非運動性、桿菌株の偏性嫌気性細菌を単離した。これをZ1-71 株と呼ぶ。細胞は長さ2.7-4.8
株と呼ぶ。細胞は長さ2.7-4.8 m、幅0.4
m、幅0.4 mであり、温度10-42
mであり、温度10-42 C、pH 6.0-9.0及びNaCl濃度0-3.0%(w/v)で生育が認められた。Z1-71
C、pH 6.0-9.0及びNaCl濃度0-3.0%(w/v)で生育が認められた。Z1-71 株は、D-グルコースを基質として生育した場合、水素の生成が認められた。16S rRNA遺伝子配列の系統解析により、Z1-71
株は、D-グルコースを基質として生育した場合、水素の生成が認められた。16S rRNA遺伝子配列の系統解析により、Z1-71 株は
株は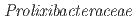 科の
科の 属に分類されることが示された。系統学的および表現型の特徴に基づき、Z1-71
属に分類されることが示された。系統学的および表現型の特徴に基づき、Z1-71 株は
株は 属の新種細菌であると考えられ、
属の新種細菌であると考えられ、 sp. nov.と命名する。Z1-71
sp. nov.と命名する。Z1-71 株を水素資化性メタン生成菌(
株を水素資化性メタン生成菌( T10
T10 株)とグルコースを基質として30
株)とグルコースを基質として30 Cの嫌気環境下で4週間共培養した結果、各単離株のみでの培養では見られなかったメタンの生成が認められた。このことは、Z1-71
Cの嫌気環境下で4週間共培養した結果、各単離株のみでの培養では見られなかったメタンの生成が認められた。このことは、Z1-71 株より生成したギ酸塩と水素がメタン生成菌により利用されることでメタンが生成したことを示していると考えられた。
株より生成したギ酸塩と水素がメタン生成菌により利用されることでメタンが生成したことを示していると考えられた。
武井 早憲
Journal of Nuclear Science and Technology, 45 Pages, 2025/06
日本原子力研究開発機構では、マイナーアクチニドを効率的に核変換する加速器駆動核変換システム(ADS)の研究開発を行っている。このシステムは、未臨界炉と大強度超伝導陽子線形加速器(ADS用陽子加速器)の組み合わせである。ADS用陽子加速器の開発を困難にしている要因の一つは、熱サイクル疲労を誘因するビームトリップ事象であり、この事象によって未臨界炉の機器が損傷するからである。ADS用陽子加速器は大強度陽子加速器の一つであるJ-PARCリニアックと比べて電流比で32倍の差がある。従って、開発段階に応じてADS用陽子加速器のビームトリップ頻度と許容ビームトリップ頻度を比較することが必要になる。今回、J-PARCリニアックの運転データに基づく信頼度関数を使ったモンテカルロ法のプログラムを作成し、ADS用陽子加速器のビームトリップ頻度を推測した。モンテカルロ法のプログラムにより、従来の解析手法では得られなかったビームトリップ事象の時間分布が得られた。その結果、許容ビームトリップ頻度を満足するには、ビームトリップ時間が5分以上のビームトリップ頻度を現状の27%に低減しなければならないことがわかった。
Niu, X.*; Elakneswaran, Y.*; Li, A.*; Seralathan, S.*; 菊池 亮佑*; 平木 義久; 佐藤 淳也; 大杉 武史; Walkley, B.*
Cement and Concrete Research, 190, p.107814_1 - 107814_17, 2025/04
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Construction & Building Technology)Metakaolin-based geopolymers have attracted significant interest in decontaminating radioactive debris from the Fukushima nuclear accident. This study explored the incorporation of boron (B) into geopolymers using boric acid as the source, with the goal of developing B-enriched geopolymers for enhanced radionuclide immobilisation and neutron capture potential.
 C alloy measured in the electrostatic levitation furnace onboard the international space station
C alloy measured in the electrostatic levitation furnace onboard the international space station石川 毅彦*; 織田 裕久*; 小山 千尋*; 下西 里奈*; 池内 留美子*; Paradis, P.-F.*; 岡田 純平*; 福山 博之*; 山野 秀将
International Journal of Microgravity Science and Application, 42(2), p.420202_1 - 420202_10, 2025/04
Samples of stainless steel (SS) - boron carbide (B C) alloys were levitated in the Electrostatic Levitation Furnace onboard the International Space Station (ISS-ELF) to measure the thermophysical properties of their melts. Melting of samples of two different compositions (SS-12.3, and 28 mass% B
C) alloys were levitated in the Electrostatic Levitation Furnace onboard the International Space Station (ISS-ELF) to measure the thermophysical properties of their melts. Melting of samples of two different compositions (SS-12.3, and 28 mass% B C) were attempted in the furnace. Even though only one sample (SS-12.3 mass% B
C) were attempted in the furnace. Even though only one sample (SS-12.3 mass% B C) could be melted, its density was successfully obtained.
C) could be melted, its density was successfully obtained.
 長期透水試験に対する再現シミュレーション
長期透水試験に対する再現シミュレーション末武 航弥*; 緒方 奨*; 安原 英明*; 青柳 和平; 乾 徹*; 岸田 潔*
第16回岩の力学国内シンポジウム講演論文集(インターネット), p.304 - 309, 2025/01
地層処分の安全性評価において、廃棄体処分坑道の掘削に伴うEDZ(掘削損傷領域)の進展範囲や、掘削後の岩盤の透水性変化挙動を予測することは非常に重要である。本研究では、三次元坑道掘削シミュレーターを用いて、幌延深地層研究センターで実施されている原位置坑道掘削とその後の透水試験を対象とした再現解析を試みた。その結果、掘削によるEDZの進展範囲と透水試験の結果について、原位置試験と類似する結果が得られた。このことから、本シミュレーターがわが国の大深度泥岩帯においての掘削に伴う力学的影響や、掘削後の岩盤変形-浸透といった連成現象とそれによる透水性変化などの予測評価に関して、有効であることが確認された。
Johansen, M. P.*; Gwynn, J. P.*; Carpenter, J. G.*; Charmasson, S.*; McGinnity, P.*; 森 愛理; Orr, B.*; Simon-Cornu, M.*; Osvath, I.*
Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 55(6), p.422 - 445, 2025/00
被引用回数:3 パーセンタイル:32.78(Environmental Sciences)Seafood is an important source for meeting future global nutrient demands. However, it also contributes disproportionately to the radiological ingestion dose of more than five billion world consumers - up to  70%-80% of the total-foods dose in some countries. Although numerous studies report seafood doses in specific populations, there is still no comprehensive evaluation answering basic questions such as "what is the ingestion dose to the average global seafood consumer?" Analysis of 238 worldwide seafood dose estimates suggests that typical adult consumers receive from 0.13 to 0.21 mSv, with a likely best estimate of 0.15 mSv per annual seafood intake. Those consuming large amounts of seafood, particularly bivalves, may experience ingestion doses exceeding 1 mSv per annual intake, surpassing other routine background dose sources. The published studies suggest that doses of 3 mSv or greater are surpassed in about 150 million adult seafood consumers worldwide. Almost all this dose comes from the natural radionuclides that are prevalent in marine systems - especially
70%-80% of the total-foods dose in some countries. Although numerous studies report seafood doses in specific populations, there is still no comprehensive evaluation answering basic questions such as "what is the ingestion dose to the average global seafood consumer?" Analysis of 238 worldwide seafood dose estimates suggests that typical adult consumers receive from 0.13 to 0.21 mSv, with a likely best estimate of 0.15 mSv per annual seafood intake. Those consuming large amounts of seafood, particularly bivalves, may experience ingestion doses exceeding 1 mSv per annual intake, surpassing other routine background dose sources. The published studies suggest that doses of 3 mSv or greater are surpassed in about 150 million adult seafood consumers worldwide. Almost all this dose comes from the natural radionuclides that are prevalent in marine systems - especially  Po. While trace levels of anthropogenic radionuclides are ubiquitous in seafoods (e.g.,
Po. While trace levels of anthropogenic radionuclides are ubiquitous in seafoods (e.g., Cs and
Cs and  Pu), the added dose from these is typically orders of magnitude lower. Even following the large-scale releases from the Fukushima accident, with food safety controls in place, the additional dose to consumers in Japan was small relative to routine dose from natural background radionuclides. However, the worldwide seafood dose estimates span seven orders of magnitude, indicating a need for an assessment that integrates global seafood radionuclide data as well as incorporating changes in seafood consumption and production patterns.
Pu), the added dose from these is typically orders of magnitude lower. Even following the large-scale releases from the Fukushima accident, with food safety controls in place, the additional dose to consumers in Japan was small relative to routine dose from natural background radionuclides. However, the worldwide seafood dose estimates span seven orders of magnitude, indicating a need for an assessment that integrates global seafood radionuclide data as well as incorporating changes in seafood consumption and production patterns.
佐藤 優樹; 角藤 壮*; 田中 孝幸*; 嶋野 寛之*
European Physical Journal; Special Topics, 10 Pages, 2025/00
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Physics, Multidisciplinary)In decommissioning the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, understanding the distribution of radioactive substances is crucial to developing detailed decontamination plans and minimizing worker exposure. In this study, an autonomous mobile radiation source detection system based on a mecanum wheel robot equipped with a Compton camera was constructed. The Compton camera visualizes the radiation source, and software embedded in the robot system reads the results to recognize the radiation source and move the robot toward it. If the robot's depth camera detects an obstacle while moving, it changes direction, visualizes the radiation source again using the Compton camera, and repeats moving the robot toward the radiation source. Furthermore, two demonstration tests were conducted in the laboratory using a  Cs radiation source to confirm that the robot can reach it where there are obstacles or a narrow region. We have also summarized issues that must be identified to apply this system to actual decommissioning sites.
Cs radiation source to confirm that the robot can reach it where there are obstacles or a narrow region. We have also summarized issues that must be identified to apply this system to actual decommissioning sites.
佐藤 里奈; 吉村 和也; 眞田 幸尚; 三上 智; 山田 勉*; 中曽根 孝政*; 金井塚 清一*; 佐藤 哲朗*; 森 翼*; 高木 毬衣*
Environment International, 194, p.109148_1 - 109148_8, 2024/12
被引用回数:1 パーセンタイル:31.14(Environmental Sciences)周辺線量当量による個人の外部被ばく線量評価は、個人線量計が適用できない、予測的及び遡及的な評価に用いられる。しかし、様々なパラメータを用いるため個人線量測定による評価よりも誤差を含む傾向がある。そこで本研究では、周辺線量当量から個人の外部被ばく線量を精度良く評価するため、生活パターンと、建物や乗り物による遮蔽効果を考慮して実効線量を評価するモデルを作成した。モデルパラメータは、2020から2021年に福島第一原子力発電所の被災地域で測定した屋内外の環境放射線のロバストなデータセットを基に評価した。モデルの精度は、2020年に福島県内で測定した106人日の個人線量と比較し評価した。モデルによる推定実効線量は、実測個人線量をよく表し、モデルが個人線量計と同様に個人の被ばく線量推計に活用できることが示された。さらに、このモデルは、環境放射線データを用いることで、個人の被ばく線量を予測的及び遡及的に精度良く評価でき、放射線防護に有用なツールである。
廃炉環境国際共同研究センター; 東京大学*
JAEA-Review 2024-021, 126 Pages, 2024/11
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和4年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等をはじめとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、令和3年度に採択された研究課題のうち、「ジオポリマー等によるPCV下部の止水・補修及び安定化に関する研究」の令和4年度分の研究成果について取りまとめたものである。本研究では、PCV底部の止水及び補修を目的として、改良したジオポリマーや超重泥水によりジェットデフレクター等を止水し、併せてドライウェル下部を補修する施工法を提案する。また、堆積状況など未解明な状況にある現場施工の選択肢を増やすため、止水・補修材の対象部位周辺への局所的施工のみならず、ペデスタル外の広範囲にわたる施工についても検討し、最新の熱流動シミュレーション法により、工法実現性を評価する。広範囲に施工する場合には、ペデスタル外に流出した燃料デブリや堆積物は止水・補修材で被覆されて廃棄体となる。このため、燃料デブリの成層化状態等性状を実験及び解析により把握した上で、廃棄体を安定化する方策を検討するとともに、核種浸出性を含めた廃棄体の長期寿命を評価する。
 from 3-GeV protons and
from 3-GeV protons and  Hg with the
Hg with the  Bi(n,xn) reactions
Bi(n,xn) reactions杉原 健太*; 明午 伸一郎; 岩元 大樹; 前川 藤夫
JAEA-Conf 2024-002, p.162 - 167, 2024/11
中性子エネルギースペクトルは加速器駆動システム(1.5GeV p+鉛ビスマス共晶合金)における遮蔽設計にとって重要である。同様のスペクトルはJ-PARC(3GeV陽子+ Hg)でも得られる。アンフォールディングの妥当性を確認するため、
Hg)でも得られる。アンフォールディングの妥当性を確認するため、 Bi(n,xn)反応と応答関数(JENDL/HE-2007とTALYS)を用いたアンフォールディングを行った。ポスターでは、スペクトルの導出と飛行時間法を用いたスペクトルとの比較を発表する。
Bi(n,xn)反応と応答関数(JENDL/HE-2007とTALYS)を用いたアンフォールディングを行った。ポスターでは、スペクトルの導出と飛行時間法を用いたスペクトルとの比較を発表する。
Zheng, X.; 玉置 等史; 柴本 泰照; 丸山 結
日本原子力学会誌ATOMO , 66(11), p.565 - 569, 2024/11
, 66(11), p.565 - 569, 2024/11
原子力安全の継続的な改善のためにはリスク情報と不確かさ情報を活用した合理的な意思決定が重要であり、近年ではこれを効率的に実施するために人工知能/機械学習(AI/ML)を活用することが期待されている。本報では、原子力分野におけるAI/MLの活用例を調査し、日本原子力研究開発機構が行うAI/MLを活用した動的確率論的リスク評価(PRA)と不確かさ評価・感度解析の研究状況を紹介する。具体的には、決定論的解析コードと機械学習による代替評価モデルを柔軟に共用できる多忠実シミュレーション手法を構築することで、ランダムサンプリングを用いた動的PRAとソースターム不確かさ評価・グローバル感度解析の効率的な実施を可能とした。
江村 優軌; 松場 賢一; 菊地 晋; 山野 秀将
Proceedings of 13th Korea-Japan Symposium on Nuclear Thermal Hydraulics and Safety (NTHAS13) (Internet), 8 Pages, 2024/11
Assuming the CDA of SFRs, the eutectic melting between B C as a control rod material and stainless steel (SS) as a structural material could occur below their melting points. After that, the mixture produced by eutectic melting between B
C as a control rod material and stainless steel (SS) as a structural material could occur below their melting points. After that, the mixture produced by eutectic melting between B C and SS (B
C and SS (B C-SS mixture) would relocate inside or outside of the original core region. From the viewpoint of core reactivity changes, the relocation behavior of B
C-SS mixture) would relocate inside or outside of the original core region. From the viewpoint of core reactivity changes, the relocation behavior of B C-SS mixture induced by its melting/freezing behavior, is one of the key elements to evaluate the CDA consequences. Many experimental studies on freezing behavior using core materials and its simulants, including molten UO
C-SS mixture induced by its melting/freezing behavior, is one of the key elements to evaluate the CDA consequences. Many experimental studies on freezing behavior using core materials and its simulants, including molten UO , SS, tin, wood's metal have been reported in the past. Based on these experimental findings, the freezing/blockage model for the severe accident simulation code was established and discussed through analyses of freezing process. Specifically, it has been considered that the experimental correlation of melt-penetration length was a key indicator to quantitatively describe freezing behavior. However, there was no experimental data for the freezing behavior of actual B
, SS, tin, wood's metal have been reported in the past. Based on these experimental findings, the freezing/blockage model for the severe accident simulation code was established and discussed through analyses of freezing process. Specifically, it has been considered that the experimental correlation of melt-penetration length was a key indicator to quantitatively describe freezing behavior. However, there was no experimental data for the freezing behavior of actual B C-SS mixture. Therefore, the freezing experiments of B
C-SS mixture. Therefore, the freezing experiments of B C-SS mixture were conducted to investigate the freezing and blockage behavior inside a flow path such as fuel pin bundle. In the freezing experiments, B
C-SS mixture were conducted to investigate the freezing and blockage behavior inside a flow path such as fuel pin bundle. In the freezing experiments, B C powder and SS block were heated up to around 1,750 K using a graphite heating furnace, then B
C powder and SS block were heated up to around 1,750 K using a graphite heating furnace, then B C-SS mixture flowed down into an SS pipe for cooling below 750 K. The experimental results showed that the B
C-SS mixture flowed down into an SS pipe for cooling below 750 K. The experimental results showed that the B C-SS mixture solidified and resulted in the blockage in the SS pipe with 4 mm or 6.7 mm in inner diameter, respectively. Furthermore, the observations for cross section of SS pipe suggested that the B
C-SS mixture solidified and resulted in the blockage in the SS pipe with 4 mm or 6.7 mm in inner diameter, respectively. Furthermore, the observations for cross section of SS pipe suggested that the B C-SS mixture penetrated deeper than molten SS. This difference is considered to be influenced by decrease of the melting point.
C-SS mixture penetrated deeper than molten SS. This difference is considered to be influenced by decrease of the melting point.
廃炉環境国際共同研究センター; 東京工業大学*
JAEA-Review 2024-026, 80 Pages, 2024/10
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和4年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という。)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下、「1F」という。)の廃炉等をはじめとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、令和元年度に採択された研究課題のうち、「放射線・化学・生物的作用の複合効果による燃料デブリ劣化機構の解明」の令和元年度から令和4年度分の研究成果について取りまとめたものである。本研究は、放射化学、核化学、核物理、燃料材料科学の専門家に環境微生物の専門家を加えた研究者により、模擬デブリの作製から、照射、化学的作用及び生物作用による溶出試験を行い、富岡町の国際共同研究棟等にJAEAが有する先端分析機器を駆使してデブリの性状の変化、元素の溶出挙動を分析し、放射線損傷と酸化環境下における化学的及び生物学的損傷の複合作用による燃料デブリの劣化機構を解明することを目的とした。令和4年度には、放射線・化学・生物的作用の複合効果による燃料デブリ劣化機構の解明のため、 線照射下における微生物の模擬燃料デブリ劣化試験、Feと錯形成能を有するシデロフォアであるdesferrioxamine (DFO)あるいは代替物とFe、Uの錯形成能、模擬燃料デブリやマイクロ粒子を計測できるマイクロ流路を用いた溶解試験、Fe酸化物への収着へのシデロフォアなどの影響、モデル微生物や1F付近で採取した菌種による模擬燃料デブリの劣化に関する知見を実験により得た。更に、模擬デブリの劣化を時間の関数として表すモデルを作成し、計算を行った。
線照射下における微生物の模擬燃料デブリ劣化試験、Feと錯形成能を有するシデロフォアであるdesferrioxamine (DFO)あるいは代替物とFe、Uの錯形成能、模擬燃料デブリやマイクロ粒子を計測できるマイクロ流路を用いた溶解試験、Fe酸化物への収着へのシデロフォアなどの影響、モデル微生物や1F付近で採取した菌種による模擬燃料デブリの劣化に関する知見を実験により得た。更に、模擬デブリの劣化を時間の関数として表すモデルを作成し、計算を行った。
Battulga, B.; 中西 貴宏; 安藤 麻里子; 乙坂 重嘉*; 小嵐 淳
Environmental Science and Pollution Research, 31, p.60080 - 60092, 2024/10
プラスチックの破片が水生環境および陸上環境で遍在的に分布していることが報告されている。しかし、プラスチックと放射性核種との相互作用や、環境プラスチックの放射能についてはほとんど知られていない。今回われわれは、環境中のプラスチックと放射性セシウム( Cs)の間の相互作用媒体としてのプラスチック関連バイオフィルムの役割を調査するためにプラスチック破片の表面で発達するバイオフィルムの特徴を調べる。バイオフィルムサンプルは日本の二つの対照的な沿岸地域から収集されたプラスチック(1-50mm)から抽出された。プラスチックの放射能は、バイオフィルムの
Cs)の間の相互作用媒体としてのプラスチック関連バイオフィルムの役割を調査するためにプラスチック破片の表面で発達するバイオフィルムの特徴を調べる。バイオフィルムサンプルは日本の二つの対照的な沿岸地域から収集されたプラスチック(1-50mm)から抽出された。プラスチックの放射能は、バイオフィルムの Cs放射能濃度に基づいて推定され、周囲の環境サンプル(つまり、堆積物や砂)と季節ごとに比較された。
Cs放射能濃度に基づいて推定され、周囲の環境サンプル(つまり、堆積物や砂)と季節ごとに比較された。 Csの痕跡は、バイオフィルムの放射能濃度21-1300Bq kg
Csの痕跡は、バイオフィルムの放射能濃度21-1300Bq kg (乾燥重量)のバイオフィルムで検出され、これは0.04-4.5Bq kg
(乾燥重量)のバイオフィルムで検出され、これは0.04-4.5Bq kg プラスチック(乾燥重量)に相当する。われわれの結果は
プラスチック(乾燥重量)に相当する。われわれの結果は Csとプラスチックとの相互作用を明らかにしバイオフィルム中の有機成分と鉱物成分が環境プラスチック中の
Csとプラスチックとの相互作用を明らかにしバイオフィルム中の有機成分と鉱物成分が環境プラスチック中の Csの保持に不可欠であるという証拠を提供する。
Csの保持に不可欠であるという証拠を提供する。
西原 健司; 菅原 隆徳; 福島 昌宏; 岩元 大樹; 方野 量太; 阿部 拓海
Proceedings of International Conference on Nuclear Fuel Cycle (GLOBAL2024) (Internet), 4 Pages, 2024/10
マイナーアクチニド核変換用の熱出力800MWの鉛ビスマス冷却ADSのスケールダウン版として、加速器駆動システムのパイロットプラントを提案する。本発表では、パイロットプラントの設計方針について述べる。
栗坂 健一; 西野 裕之; 山野 秀将
Proceedings of Probabilistic Safety Assessment and Management & Asian Symposium on Risk Assessment and Management (PSAM17 & ASRAM2024) (Internet), 10 Pages, 2024/10
本研究の目的は破損拡大抑制技術によって過大地震時の原子炉構造レジリエンス向上策の有効性を評価することである。安全上重要な機器・構造物のレジリエンス向上策によって耐震裕度が増すとみなす。同向上策の有効性を評価するため、炉心損傷頻度CDFを指標に選び、CDFの低減を地震PRAによって定量化する。ループ型次世代ナトリウム冷却高速炉を想定して有効性評価を実施した。地震時CDFに寄与の大きい原子炉容器RVを対象に、従来は座屈を破損とみなしていたところ、振動座屈後に安定な状態を維持する場合を想定し、疲労破損に至るまでの座屈後のRV挙動を現実的に考慮することをレジリエンス向上策とみなした。仮定した範囲内では、レジリエンス向上策は設計地震動の数倍の地震までCDFを有意に低減する効果を示した。
廃炉環境国際共同研究センター; 東京工業大学*
JAEA-Review 2024-012, 122 Pages, 2024/09
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和4年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下、「1F」という)の廃炉等をはじめとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、令和3年度に採択された研究課題のうち、「福島原子力発電所事故由来の難固定核種の新規ハイブリッド固化への挑戦と合理的な処分概念の構築・安全評価」の令和4年度分の研究成果について取りまとめたものである。本研究は、1F事故で発生した多様な廃棄物を対象とし、固定化が難しく長期被ばく線量を支配するヨウ素(I)、 核種のマイナーアクチノイド(MA)に注目し、これらのセラミクス1次固化体を、更に特性評価モデルに実績を有するSUSやジルカロイといったマトリクス材料中に熱間等方圧加圧法(HIP)等で固定化した"ハイブリッド固化体"とすることを提案する。核種閉じ込めの多重化、長期評価モデルの信頼性の向上により実効性・実用性のある廃棄体とし、処分概念を具体化する。潜在的有害度及び核種移行の観点から処分後の被ばく線量評価を行い、安全かつ合理的な廃棄体化法、処分方法の構築を目的としている。2年目の令和4年度は、1F模擬廃棄物の合成実験、各種放射線照射実験、浸出試験、ハイブリッド固化体の構造解析、固化元素の電子状態変化の放射光分析を行った。種々の計算でI固化体の固溶エネルギー、マトリクスと1次固化体との相互作用を解明した。実験と計算検討により、ヨウ素廃棄物にはマトリクスとしてSUSが適すると結論付けた。ハイブリッド固化体からの核種移行、被ばく線量に対する人工バリア、天然バリア機能の感度解析により、廃棄体寿命を長くすることが長半減期かつ難固定性のI-129には効果的であることが明らかとなった。以上により、廃棄物合成から廃棄物処分時の安全評価までの結節が達成された。
核種のマイナーアクチノイド(MA)に注目し、これらのセラミクス1次固化体を、更に特性評価モデルに実績を有するSUSやジルカロイといったマトリクス材料中に熱間等方圧加圧法(HIP)等で固定化した"ハイブリッド固化体"とすることを提案する。核種閉じ込めの多重化、長期評価モデルの信頼性の向上により実効性・実用性のある廃棄体とし、処分概念を具体化する。潜在的有害度及び核種移行の観点から処分後の被ばく線量評価を行い、安全かつ合理的な廃棄体化法、処分方法の構築を目的としている。2年目の令和4年度は、1F模擬廃棄物の合成実験、各種放射線照射実験、浸出試験、ハイブリッド固化体の構造解析、固化元素の電子状態変化の放射光分析を行った。種々の計算でI固化体の固溶エネルギー、マトリクスと1次固化体との相互作用を解明した。実験と計算検討により、ヨウ素廃棄物にはマトリクスとしてSUSが適すると結論付けた。ハイブリッド固化体からの核種移行、被ばく線量に対する人工バリア、天然バリア機能の感度解析により、廃棄体寿命を長くすることが長半減期かつ難固定性のI-129には効果的であることが明らかとなった。以上により、廃棄物合成から廃棄物処分時の安全評価までの結節が達成された。
Battulga, B.; Munkhbat, D.*; 松枝 誠; 安藤 麻里子; Oyuntsetseg, B.*; 小嵐 淳; 川東 正幸*
Environmental Pollution, 357, p.124427_1 - 124427_10, 2024/09
被引用回数:1 パーセンタイル:31.14(Environmental Sciences)水生環境および陸上環境におけるプラスチック破片の発生とその特徴は、広範囲に研究されてきた。しかし、環境中のプラスチック関連バイオフィルムの特性と動的挙動に関する情報はまだ限られている。この研究では、モンゴルの内陸河川系からプラスチックサンプルを収集し、分析、同位体、熱重量分析技術を使用してプラスチックからバイオフィルムを抽出し、バイオフィルムの特性を明らかにした。抽出されたバイオフィルムから有機粒子と鉱物粒子の混合物が検出され、プラスチックが河川生態系の汚染物質を含む外因性物質のキャリアであることが明らかになった。熱重量分析により、バイオフィルムの約80wt%を占めるアルミノケイ酸塩と方解石を主成分とするミネラルが主に寄与していることが示された。本研究は、水生生態系における有機物および物質循環に対するプラスチック関連バイオフィルムの影響を解明するのに役立つ、バイオフィルムの特性および環境挙動に関する洞察を提供する。
Chen, H. F.*; Liu, B. X.*; 徐 平光; Fang, W.*; Tong, H. C.*; Yin, F. X.*
Journal of Materials Research and Technology, 32, p.3060 - 3069, 2024/09
被引用回数:1 パーセンタイル:0.00(Materials Science, Multidisciplinary)The hot-rolled microstructure of medium Mn steel has coarse grains and severe elemental segregation, resulting in low strength and plasticity. Constructing a multiphase structure, refining the microstructure, and regulating elemental segregation enhance the mechanical properties. In this study, liquid nitrogen treatment created a layered distribution of austenite and martensite. Warm rolling was then used to reduce layer thickness and refine grain structure. After liquid nitrogen and warm rolling treatments, the strength and plasticity of medium Mn steel increased to 1270 MPa and 23.3%, respectively, far exceeding the hot-rolled state (724 MPa, 12.8%). Warm rolling also triggers austenite reverted transformation (ART) and introduces high-density dislocations, further improving austenite stability. This strengthening effect is higher than that from intercritical annealing alone. Improved austenite stability delays the transformation induced plasticity (TRIP) effect, preventing brittle fracture and enhancing deformation coordination between layers, significantly increasing the plastic deformation capacity of medium Mn steel.
田中 琢朗*; 福岡 将史*; 戸田 賀奈子*; 中西 貴宏; 寺島 元基; 藤原 健壮; 庭野 佑真*; 加藤 弘亮*; 小林 奈通子*; 田野井 慶太朗*; et al.
ACS ES&T Water (Internet), 4(8), p.3579 - 3586, 2024/08
Radioactive cesium released by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident in March 2011 remains in the forest environment and is being transported to the ocean via residential areas by runoff into river systems. Most of the  Cs in river water exists as suspended forms, being strongly fixed by micaceous clay minerals. If this fraction can change its form into dissolved forms, this results in additional input of bioavailable
Cs in river water exists as suspended forms, being strongly fixed by micaceous clay minerals. If this fraction can change its form into dissolved forms, this results in additional input of bioavailable  Cs. In this study, in-situ sampling of
Cs. In this study, in-situ sampling of  Cs at multiple rivers in Fukushima Prefecture was conducted using the DGT (diffusive gradient in thin film) devices to investigate the dynamics of radioactive cesium in river environments. At almost all sampling points, the DGT
Cs at multiple rivers in Fukushima Prefecture was conducted using the DGT (diffusive gradient in thin film) devices to investigate the dynamics of radioactive cesium in river environments. At almost all sampling points, the DGT  Cs concentrations exceeded dissolved
Cs concentrations exceeded dissolved  Cs concentrations, revealing the existence of a flux from the suspended to the dissolved forms. This additional input was found to have higher
Cs concentrations, revealing the existence of a flux from the suspended to the dissolved forms. This additional input was found to have higher  Cs/
Cs/  Cs ratios, compared those of Cs in the dissolved form. This study demonstrates that the bioavailability of
Cs ratios, compared those of Cs in the dissolved form. This study demonstrates that the bioavailability of  Cs can be underestimated by assessing only the dissolved form due to
Cs can be underestimated by assessing only the dissolved form due to  Cs flux from the suspended particles likely caused by their dissolution.
Cs flux from the suspended particles likely caused by their dissolution.